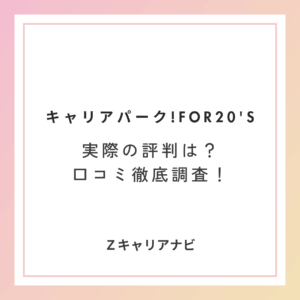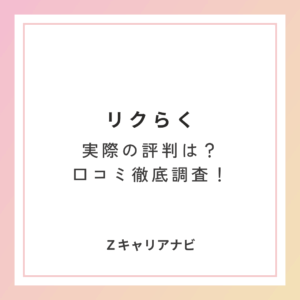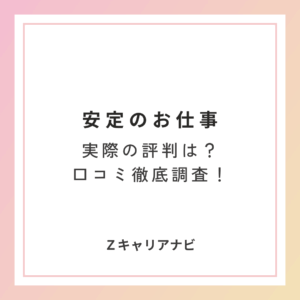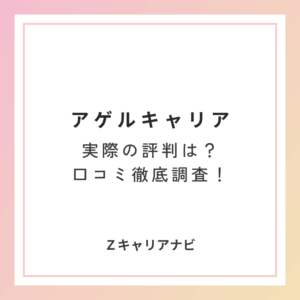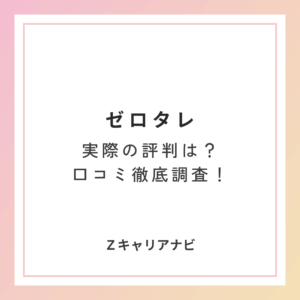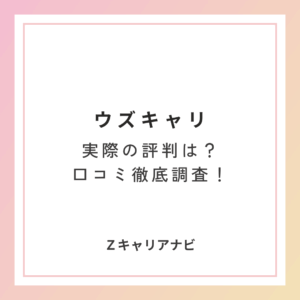「既卒者としての面接、新卒とはどう違うんだろう?」
「面接でどんなことを答えればいいのかわからない…」
このような疑問や不安を抱えている既卒の方は多いのではないでしょうか。
若手の人手不足が話題になる現代では、既卒者を受け入れる企業も増えてきたといわれています。
とはいえ、自分がきちんと面接を通過できるかどうか、希望する企業に入れるかどうかが不安になるのは当然の心理だといえます。
本記事では、昨今の既卒採用の大まかな傾向について解説し、既卒者が面接を突破するために必要な情報を詳しく説明します。
ぜひ最後まで読んで、自信を持って面接に向かえる状態を目指してください。
| エージェント名 | 評価 | ポイント |
|---|---|---|
 >>キャリアスタート公式へ >>キャリアスタート公式へ |
高待遇の求人を多数保有し、高年収も目指せる! | |
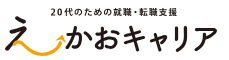 >> えーかおキャリア公式へ >> えーかおキャリア公式へ |
充実したサポートで定着しやすい企業に出会える! | |
 >>アメキャリ公式へ >>アメキャリ公式へ |
平均12時間のサポートで給与アップして就職可能! |
目次
既卒採用の近年の動向について
既卒学生の採用枠は、近年どんどん拡大されています。
人口が減りつつある日本において20代の若手社員の価値が相対的に上がり、企業側の考え方も「若い人を採用してやろう」から「どうすれば若い人が入ってくれるか」にシフトしつつあるのです。
実際、株式会社マイナビの「2024年卒企業新卒採用予定調査」では、70%以上の企業が「既卒者の応募受け入れをおこなっている」と回答しています。
2012年度の同調査では、既卒者を受け入れていると答えた企業は40%でした。就職活動の市場には、かなり大きな変化が訪れているといえるでしょう。
ただし、既卒ならではの難しさもあります。
多くの企業は採用ページに既卒者向けの情報を掲載していません
そのため既卒者側も「この企業に応募しても大丈夫だろうか」とためらってしまい、企業探しに苦戦しているのです。
また、新卒と同様の待遇で受け入れるとはいっても、面接では「なぜ新卒で就職しなかったのか」という質問が高確率でおこなわれるでしょう。そこに引け目を感じ、応募しづらさを抱えている既卒者も多く見られます。
ですが、実際には多くの企業が若手社員を求めています。既卒者だからといって遠慮せず、積極的に応募してみることをおすすめします。
まずは面接の基本的な流れをチェック
面接は、企業と求職者がお互いを知り、一緒に働けるかどうかを確かめ合う貴重な場です。せっかくのチャンスだからこそ、念入りに準備をしておく必要があります。
自信を持って面接の場に臨むために、まずは基本的な流れを確認しておきましょう。
面接の基本的な流れ
- 面接前の準備
- 面接会場への移動から待機時間にかけて
- 面接開始後の具体的な流れ
- 面接終了後の動きについて
面接前の準備
面接を受ける前におこなうべき準備は「話す内容の掘り下げ」と「書類や服、その他の持ち物といった物理的な準備」の2種類に大きく分けられます。
どちらが欠けても面接では面接官に悪い印象を残してしまうため、両方ともしっかり準備することが重要です。
まず、話す内容の掘り下げです。
自己PRや志望動機は書類に書くだけでなく、口頭でもわかりやすく話せるように練習しておきましょう。書類では200~300字程度に短くまとめる必要がありますが、実際に話す場面ではもう少し長くなるのが一般的です。
なかには、練習不足のまま面接に挑んだ結果、緊張のせいで具体的なエピソードが思い出せず支離滅裂な話をしてしまう人もいますが、それではもったいないです。
自己PRなどの高確率で聞かれる項目については、必ず話す内容全体の原稿を別途作り、内容を覚えておきましょう。
物理的な準備としては、応募書類、スーツ、革靴やカバン、腕時計などが挙げられます。面接当日に慌てることがないよう、前日の時点で「今すぐ出発できる状態」まで整えておきましょう。
また、移動時間についてもあらかじめ複数のパターンを調べ、余裕を持ったスケジュールを立てておくのがおすすめです。
面接会場への移動から待機時間にかけて
面接を受ける際には、当日の移動に備えた準備も必要です。
公共交通機関の乗り換えルートを調べ、最寄駅から会場となる建物までの道順も確認しておきましょう。
地図アプリも有効ですが、あらかじめGoogleマップのストリートビューなどを活用して具体的な道筋まで覚えておくのがおすすめです。
また、交通系電子マネーの残高も前日までに確認し、あらかじめチャージしておきましょう。事前に考えておいた乗り換えプランが崩れるリスクを防ぐだけでなく「チャージしたから大丈夫」という精神的な安心感としても一役買ってくれます。
会場付近には15~20分くらい前に着いておき、10分前を目安に受付を済ませます。
建物に入ってからはもう面接が始まっている意識を持ち、姿勢を正して過ごすよう心掛けましょう。
一方、オンライン面接の場合も事前のチェックは必要です。使用する端末と通信環境の事前テストは必ずおこないましょう。
たとえば「リビングなら問題ないのに自室では遅延する」といったトラブルは頻出です。
ZOOMやGoogle Meetのようなオンライン会議システムは、一般的なネットの閲覧よりも頻繁にサーバーにアクセスし、リアルタイムの情報をアップロード・ダウンロードしているため、きちんとそのシステムでの動作確認をしておくことをおすすめします。
このように、オンライン・オフライン問わず、当日思わぬトラブルに巻き込まれる可能性を極限まで減らしておくという意識が重要です。
面接開始後の具体的な流れ
面接の基本的な流れは以下のようなものが一般的です。
1.アイスブレイク
面接の初めは「今日はどのように来たか」「緊張しているか」など、お互いの気持ちをほぐすようなやりとりから入る場合が一般的です。
ここでの回答が合否に影響する確率は低いため、素直に会話を進めるだけで問題ありません。
2.面接官による企業説明や求人内容の説明
一次面接の場合、序盤で面接官からその企業についての説明や、今回の求人内容についての詳しい説明、そして面接官自身の自己紹介がおこなわれます。
ただし、事前に会社説明会に参加していたり、既に面談等で企業の人との接点があった場合には、省略される場合もあるでしょう。
3.応募者の自己紹介・自己PR
企業側の説明が一通り終わったら、いよいよこちらが自己紹介をする番です。
自己紹介や自己PRの内容はあらかじめ考えておき、1~2分ほどでスムーズに話せるようにしておきましょう。
自己紹介のタイミングで、自分をアピールしようと思うあまり、これまでの経歴を細かく時系列に沿って説明してしまう人もいますが、これはNGです。
また、この時点で自分の強みや詳細な志望動機について語り始めるのも「自己紹介をしてください」という相手の質問の意図から逸れてしまうため、避けておいた方が良いでしょう。
面接の本番はあくまでこの後の質疑応答であることを念頭に置き、簡潔な自己紹介を心掛けましょう。
4.面接官から応募者への質疑応答
ここからは、志望動機や応募者自身のパーソナリティに関する質問、将来の展望に関する質問など、さまざまな質問がおこなわれます。
一般的な面接での質問には一通り答えられるよう、回答の内容は事前に準備しておきましょう。
とくに、志望動機や入社後に取り組みたい仕事については、その企業についてしっかり研究し、具体的な内容を述べられる状態にしておく必要があります。
また、既卒者の場合は「なぜ新卒で就職しなかったのか」「卒業してからこれまでどのように過ごしてきたのか」という質問への回答準備が必須です。
既卒であること自体がマイナス評価になるわけではありませんが、これらの質問への回答がいい加減だと、面接官からの印象が一気に悪くなってしまうため注意が必要です。
5.応募者から面接官への逆質問
面接官からの質問が一通り終わったら、次は「何か質問はありますか」「今聞いておきたいことは他にありますか」といった形で逆質問が始まります。
ここで「何もありません」と答えることは、あまりおすすめしません。
その企業に関する興味が薄いのではないかと相手に思われてしまうため、マイナスの評価につながります。
逆質問で尋ねる内容は事前にいくつか用意しておき、先ほどの質疑応答の間に出てこなかったテーマを質問しましょう。
基本的にはここまでで面接は終了となります。
建物を出る瞬間まで気を抜かず、礼儀正しく挨拶をしてから退出しましょう。
スマホのチェックなども、建物を完全に出てからするのが無難といえるでしょう。
面接終了後の動きについて
面接が終わったら、その日のうちに「今回の面接はどうだったか」という振り返りをおこないましょう。
良かった点、悪かった点をそれぞれ書き出し、次回以降の面接に活かすことが重要です。
なかには、「緊張で真っ白になって内容を何も覚えていない…」という人もいるかもしれませんが、それはそれで「少しでも緊張せずに面接を受けるためには何をすればいいか」を考えるきっかけとなります。
また、できれば当日の営業時間内にお礼のメールを送るのも効果的です。件名は「〇月〇日 面接のお礼 氏名」とし、簡潔にお礼の言葉を述べましょう。
先方からの合否の連絡を待っている間は、自分の今後のスケジュールを整理し、把握しておくのがおすすめです。
合否の連絡はメールで届く例が一般的ではありますが、企業によっては電話で「合格です。次の面接はいつ来られますか」と聞かれる可能性もあります。
「確認して再度ご連絡いたします」でも大きな問題はないのですが、その場で返答した方がお互いにスムーズです。
既卒者が面接でよく聞かれる質問と回答例10選
ここからは、既卒者が就職面接でよく聞かれる質問と、理想的な回答のしかたについて紹介します。
質問への準備が足りないまま面接に行くと、話の内容がまとまらず「何を言いたいのかわからない」と思われたり「この人は本当にうちの会社に入りたいのだろうか」と思われたりします。
すべてを丸暗記する必要はありませんが、どんな内容をどういった順序で話すのか、大まかな構成までは頭に入れた状態で面接に臨みましょう。
1:「自己紹介をしてください」
冒頭での自己紹介は名前程度で済ませ、質疑応答に入ってから改めて「自己紹介を」と言われるパターンもあります。
面接冒頭で聞かれた際と同じく、1~2分で簡潔に答えられるようにしておきましょう。
自己紹介の回答例
〇〇(氏名)です。A大学B学部をXXXX年に卒業し、現在〇歳です。
大学卒業後、現在までは~~~~をおこなっていました。しかし、将来を見据えて正社員としてのキャリアを積みたいと思い、特に〇〇という仕事に強い興味を抱いたため、この度応募させていただきました。
本日はよろしくお願いいたします。
2:「自己PRをしてください」
自己紹介と併せて求められるのが自己PRです。自分自身の強みやスキルを述べ、企業でどのように役に立てるかをアピールしましょう。
その際には、具体的なエピソードも一緒に話すのが一般的です。
多くのエピソードを並べるよりは、1つの体験に絞り、実際の数値なども用いて説明するのが良いでしょう。
自己PRの回答例
私の強みは、主体的に考え、常に改善を目指して行動できる点です。この力は、3年間の大手家電量販店でのアルバイト経験を通じて培いました。
私は大学時代から5年間、家電量販店の店頭販売スタッフのアルバイトを継続しています。以前、お客様の売り場での動きを分析し、売り場レイアウトの改善案を店長に提案したことがあります。関連商品を近接して配置することで、客単価が平均5000円程度向上し、店舗の売上増加に貢献できました。
このように、上司から頼まれていなくても、自分なりに職場の改善案を考え、積極的に提案できるところを活かし、貴社の営業部門でも売り上げアップに貢献したいと考えています。
3:「志望動機は何ですか」
志望動機は就職面接において、もっとも重要な質問であるといえます。
志望先企業についてどれほどの研究をおこない、どこまで具体的なイメージを抱けているのかをアピールする絶好の機会となるからです。
ポイントは「その企業だからこそ」という要素をしっかりと言葉にすることです。他の企業には使いまわせないような回答を用意しておきましょう。
志望動機の回答例
私が貴社を志望したのは、貴社のイベント企画に対する真摯な姿勢に共感したからです。先日参加した貴社の会社説明会で、イベント企画の裏側にある考え方や工夫について詳しく説明していただき、とても興味深く感じました。
特に印象に残ったのは、参加者の期待を超える体験を提供するために、細部まで配慮を重ねる姿勢です。例えば、会場レイアウトの工夫やタイムスケジュールの組み方など、一見些細に思える点にも理由があり、それが全体の満足度向上につながるという説明は、目から鱗が落ちる思いでした。
他社の説明会にも参加しましたが、貴社ほど企画の意図や過程を丁寧に説明してくれる企業は他になく、この分野への深い理解と情熱を感じました。私も、イベントを通じて人々に価値ある体験を提供したいという思いがあり、貴社で働くことでその実現方法を学びたいと考えたため、この度応募いたしました。
4:「自分の長所と短所について教えてください」
面接で自分の長所や短所を答える際には、志望先の企業で役に立ちそうな内容を選ぶのがおすすめです。
たとえば、営業職であれば行動力や粘り強さ、事務職であれば計画性や作業の丁寧さといった具合に、自分の性格のなかでなるべく志望する業務と合致するものを選びます。
だからといって、嘘をつくことはおすすめしません。あくまでも「こういう傾向があるな」という部分から答えましょう。
短所については「それを改善するためにどのような工夫をしているか」も併せて答えましょう。
長所と短所を聞かれたときの回答例
私の長所は粘り強さと顧客志向の姿勢です。大学時代に、研究プロジェクトの一環で多数の企業にアンケート調査をおこない、根気よく声を掛け続けた結果、92%という高い回答率を達成した経験があります。このことから、諦めずに取り組む力を身につけました。
一方で、短所は細部にこだわりすぎる点です。プレゼンの準備で、細かい表現にこだわり過ぎたせいで、全体構成の見直しが不十分になったことがあります。現在はタスクリストで優先順位を明確にし、効率的に物事を進める工夫をしています。これらの経験を活かし、貴社の製品の細かな特徴を理解しつつ、顧客ニーズに合わせたバランスの取れた提案ができると考えています。
5:「なぜ既卒を選んだのですか(なぜ新卒で就職しなかったのですか)」
既卒の面接を受ける以上、どうしても避けられないのがこの「なぜ既卒を選んだのか、なぜ新卒で就職しなかったのか」という質問です。
ですが、これは決して応募者を責めるためにおこなわれているわけではありません。
そもそも既卒=悪だと考える企業であれば、既卒者を面接には呼びません。
失敗してしまった部分は素直に認めながら、自信を持って前向きな回答を心掛けましょう。
既卒を選んだ/新卒で就職したなかった理由の回答例
新卒時には、正直なところ、さまざまな業界に興味が分散してしまい、深い研究ができていませんでした。IT、金融、製造業など、あれこれ考えるうちに時間がどんどん過ぎ、結果的に中途半端な就活になってしまいました。
しかし、この経験は無駄ではなかったと考えています。さまざまな業界について調べ、実際に選考の場にも足を運んだことで、自分の中の価値基準が明確になり、本当にやりたい仕事がどんなものであるのかが明確になりました。特に、IT業界の中でもAIの分野に強い関心を持つようになり、この1年間でAIの知識を深めてきました。この1年間の経験と学びを活かし、貴社の一員として技術革新と社会貢献に携わりたいと考えています。
6:「なぜ今回正社員として就職しようと決意したのですか」
この質問も、既卒者の就職面接では高確率で登場します。面接官がこの質問をする目的は、応募者の仕事への考え方やキャリアに対する真剣さを確かめることです。
そのため、企業の一員としてどのように取り組んでいきたいのか、将来のキャリアプランはどのようなものかを明確に述べる必要があります。
正社員として就職しようと思った理由の回答例
大学を卒業してからこれまで、アルバイトと並行して業務委託でプログラミングの仕事をしてきました。特にアプリ開発の領域に強い関心を持つようになり、プロフェッショナルとしてこの分野でより大きなキャリアを築いていきたいと考えるようになりました。正社員として就職することで、長期的な視点でスキルを磨き、より責任ある立場で大きな仕事に取り組めるのではないかと考えています。また、組織の一員として成長し、会社の発展に貢献したいという思いも強く持っています。
7:「ブランク期間は何をしていましたか」
大学を卒業した後の経験について質問された際には、具体的に取り組んでいたことだけでなく、そのときに考えたことや努力したことも併せて述べましょう。
目的意識を持って主体的に行動していたことをしっかりと示せれば、マイナスの印象を残さずに済むでしょう。
ブランク期間に関する質問への回答例
ブランク期間中に取り組んだことは、日商簿記検定1級の取得に向けた学習です。
大学時代から会計に興味があり、まとまった時間をかけて本格的に学習することにしました。9ヶ月間、毎日8時間以上の学習時間を確保し、オンライン講座と独学を組み合わせて効率的に勉強を進めました。
特に難しかったのは連結会計や税効果会計の分野です。実際の企業の決算書を分析し、学んだ知識を実践的に応用することで理解を深めました。
結果として、日商簿記検定1級に合格することができました。この過程で培った粘り強さと分析力を、貴社の業務でも活かしていきたいと考えています。
8:「入社後はどのような仕事をしたいですか」
入社後に何をしたいかという質問は、本人の希望を聞き取るだけでなく、その企業の業務に対してどれくらい具体的なイメージを持てているかも確かめるためにおこなわれます。
そのため、業界や職種全体に対する漠然としたイメージではなく「この企業のこの仕事に携わりたい」と具体的な希望を述べる必要があります。
この質問は、企業研究の深さを問われる質問だと認識しておきましょう。
入社後やりたい仕事に関する質問への回答例
入社後は、人事部門の採用チームに加入し、会社にマッチする人材の採用や、社員のキャリア開発支援に携わりたいと考えています。大学卒業後に地域の若者支援NPOでボランティアをおこない、若者一人ひとりの相談に乗りながら、その人たちの強みや可能性を見つけ出し、適切なアドバイスをするという活動に大きなやりがいを感じたからです。
また、貴社が推進する「リモートファースト」の働き方にも強い関心を抱いています。特に、リモートワークが広まる時代だからこその採用・育成方法の開発に挑戦したいです。たとえば、リモートワークに適した研修方法や、顔を合わせないことによる帰属意識の低下を食い止める方法の考案など、新たなコミュニケーションの形を作り出していきたいです。
9:「就活の軸は何ですか」
就職活動において「就活の軸」を明確にすることは非常に重要です。
これはその人の価値観や将来のキャリアビジョンを包括する大きな基準となります。
面接官は就活の軸を聞くことで、応募者の自己理解の深さ、キャリアプランの具体性、そして業界や企業研究の深さを確認しようとしています。
就活の軸の回答例
私の就活の軸は「教育への貢献ができること」と「最新テクノロジーに触れられる環境に身を置けること」です。
私は大学時代に情報工学を専攻しており、機械学習を用いた教育支援システムの研究をおこなっていました。また、現在もプログラミング教室で講師として活動しています。AIを活用したした学習システムによって、生徒一人ひとりの理解度に合わせた指導ができ、学習効果が大きく向上することを実感しました。そこでEdTech分野に強い貴社を志望しております。
10:「今後のキャリアプランはどのようなものですか」
キャリアプランは、応募者の仕事に対する考え方そのものです。短期的、中期的、長期的な目標をそれぞれイメージしながら、具体的かつ現実的なプランを答える必要があります。
面接での回答としては、自分自身の成長だけでなく、志望先企業の業務を意識した内容であることも求められるでしょう。
キャリアプランに関する質問への回答例
私の今後のキャリアプランの土台にあるのは、スポーツテクノロジーの革新を通じて、多くの人々の健康増進に貢献していくことです。まずは、貴社のウェアラブルデバイス部門で、製品開発の基礎を学びたいと考えています。実務経験を通してスキルを磨きながら、企画から販売までのプロセスを学び、ビジネスの観点からも理解を深めたいです。
その後は、デバイス開発のマネージャーとして、開発の中心になりたいです。健康科学やデータサイエンスの理解を深め、資格の取得も目指そうと考えています。技術の進化に合わせてさまざまなことを学び、時代に合わせたヘルスケア製品の開発に携わっていきたいです。
既卒面接の志望動機を作成するコツ
既卒者の志望動機では、新卒とは異なる視点や経験をアピールする必要があります。ここからは、既卒ならではのポイントについて解説します。
説得力のある志望動機を作成するために、ぜひ参考にしてみてください。
既卒面接の志望動機を作成するコツ
- 企業分析をおこなう
- なぜその企業で働きたいか明確にする
企業分析をおこなう
志望動機の良し悪しは、企業分析の深さによって決まるといっても過言ではありません。
企業の事業内容、価値観、市場での位置づけ、今後の展望などを詳しく調べた上で、自分がやりたい仕事と絡めて書いていきましょう。
公式サイトだけでなく、外部サイトのニュースや社員の口コミ、SNSなども参考になるかもしれません。
また既卒者の場合、新卒よりもさらに一段階深く企業について調べていることを期待される可能性があります。
そのため、企業分析はじっくりと時間をかけて取り組みましょう。
なぜその企業で働きたいか明確にする
企業分析の結果を踏まえて、自分のキャリアプランとの接点を見つけ、志望動機に取り入れましょう。企業の理念や事業内容と自分の価値観・目標がどのように合致するか、具体的に説明することが重要です。
既卒者の強みは、卒業後の時間を通じて自己分析を深め、より明確なキャリアビジョンを持てる機会があったことです。
その視点から、企業との相性を具体的に説明することで、明確な目的意識を持った人材であることをアピールできるでしょう。
| エージェント名 | 評価 | ポイント |
|---|---|---|
 >>キャリアスタート公式へ >>キャリアスタート公式へ |
高待遇の求人を多数保有し、高年収も目指せる! | |
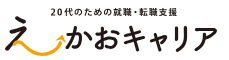 >> えーかおキャリア公式へ >> えーかおキャリア公式へ |
充実したサポートで定着しやすい企業に出会える! | |
 >>アメキャリ公式へ >>アメキャリ公式へ |
平均12時間のサポートで給与アップして就職可能! |
既卒面接を成功させるための5つのポイント
既卒者の面接では、卒業の期間をどのように活躍したかを前向きに伝えることが重要です。
ここからは、面接で相手に良い印象を残すためのポイントを5つの観点から紹介します。
既卒面接を成功させるための5つのポイント
- 既卒ならではの強みをアピールする
- 自信を持って堂々と振る舞う
- 第一印象で好感度をアップさせる
- オンライン面接にも的確に対応する
- 模擬面接で場慣れしておくのもオススメ
1.既卒ならではの強みをアピールする
既卒期間中の経験や学びを、自己の強みとして積極的にアピールしましょう。
たとえば、アルバイトやボランティア活動での経験、自己啓発の取り組み、資格取得などが挙げられます。
これらの経験を通じて得た気づきや成長した点を具体的に説明し、それらが志望する企業でどのように活かせるかを明確に伝えることが重要です。
そのため、新卒とは異なる視点や経験を持つことが、既卒者としての大きな強みとなるでしょう。
2.自信を持って堂々と振る舞う
自信を持って面接に臨むためには、十分な準備が不可欠です。志望動機や自己PRを簡潔に伝える練習を重ね、予想される質問への回答をいくつか用意しておきましょう。
また、既卒期間中の経験や学びを整理し、それらが企業にどう貢献できるかを具体的に説明できるようにておくことが重要です。
姿勢を正し、適度にアイコンタクトを取りながら、はっきりとした声で話すことを心がけましょう。
自信に満ちた態度で話せれば、あなたの成長と熱意が効果的に伝わり、面接官にも好印象を与えられます。
3.第一印象で好感度をアップさせる
第一印象は面接の成否を大きく左右します。身だしなみを整え、明るく爽やかな挨拶を心がけましょう。
面接会場に入る際の姿勢や歩き方、椅子の座り方なども重要です。
事前に転職エージェント等で模擬面接を受けたり、自分の立ち居振る舞いを録画してチェックしてみるのがおすすめです。
また、面接中は面接官との目線を合わせ、適度な笑顔を心がけることで、好感度をアップさせることができます。
これらの基本的なマナーを徹底することで、真摯に就職に取り組む姿勢をアピールできるでしょう。
4.オンライン面接にも的確に対応する
近年、オンラインで面接をおこなう企業が急増しています。デジタルデバイスに疎いと思われないためにも、入念な準備が必要です。
まず安定したインターネット環境の確保、カメラやマイクの動作確認は必須です。
背景は整理整頓し、適切な照明を用意しましょう。また、画面越しでも相手に伝わるよう、表情や声のトーンにも気を配ります。
カメラ目線で話すことを意識し、オンラインでのコミュニケーションスキルをアピールしましょう。
5.模擬面接で場慣れしておくのもオススメ
本番の面接で緊張せずに臨むためには、事前の練習が効果的です。家族や友人、あるいは転職エージェントに協力してもらい、模擬面接をおこないましょう。
想定質問への回答練習はもちろん、姿勢や表情、声の大きさなども客観的に評価してもらいます。
フィードバックを基に改善を重ねることで、自信を持って本番に臨めるようになります。
また、自己分析や企業研究の不足点も発見できるでしょう。
既卒者におすすめの転職エージェント
既卒者の就職活動が、新卒と比べると難しいのは事実です。卒業後の経験を良い評価に変えるためには、プロ目線でのアドバイスが役に立つでしょう。
ここからは、既卒者におすすめの、若手のサポートが得意な転職エージェントを紹介します。
えーかおキャリア

- 20代の既卒・第二新卒に特化したサポートを提供
- マンツーマンで丁寧なキャリアカウンセリングを受けられる
- 担当キャリアアドバイザーの指名が可能
えーかおキャリアは、第二新卒・既卒・フリーターに特化した転職エージェントです。20代の若手に強みを持ち、年間6,000人以上の若手のキャリア支援実績があります。
えーかおキャリアの特徴は、他社の4倍の内定獲得率を誇る手厚いサポートにあります。
適性診断を活用した自己分析のサポートや、企業ごとに特化した面接対策など、一人ひとりに合わせた手厚いキャリア支援を受けられます。
キャリアスタート

- 既卒や第二新卒、フリーターなど若者の就職・転職支援に特化したサービス
- 未経験OKの求人も多い
- 面接対策や履歴書の添削など、サポートが手厚い
キャリアスタートは、新卒・既卒・第二新卒・フリーター・ニートなど、若年層の就職・転職支援に特化した転職エージェントです。
キャリアスタートの強みは、未公開求人の豊富さです。公開求人とは異なり、企業の本音をストレートに知ることができ、スピーディーな採用につながります。
また、マンツーマン模擬面接など、面接対策にも力を入れており、応募した企業や求職者の特性に合わせた徹底したサポートを受けられます。
マイナビジョブ20’s

- 業界大手のマイナビが運営する若手特化サービス
- 「マイナビ適性診断」を活用した一人ひとりに合わせた支援が特徴
- 転職セミナーなど有益な情報を得られるチャンスが多い
マイナビジョブ20’sは、マイナビグループが運営する、20代・第二新卒・既卒に特化した転職エージェントです。
20代若手の転職市場に精通したキャリアアドバイザーが在籍しており、適性診断を用いた客観的な分析をもとに、手厚い転職サポートを提供しています。
マイナビジョブ20’sの特徴は、「マイナビ適性診断」を活用した的確なアドバイスにあります。適性診断の結果をもとに、自分の強みを活かせる業界・職種を提案してもらえます。
また、選考通過率を高めるための応募書類の添削や、企業へのアピール方法のアドバイスなど、手厚いサポートが受けられるのも魅力です。
既卒面接を控えた方からのよくある質問
既卒での就職活動には、様々な不安や疑問がつきものです。ここからは、既卒者の方からよく寄せられる質問とその回答を紹介します。
適切な準備と前向きな姿勢があれば、既卒であることは決して不利にはなりません。
むしろ、自己分析や目標設定がしっかりしていることをアピールするチャンスとなるでしょう。
既卒面接を控えた方からのよくある質問
- 既卒の就活は不利なのでしょうか?
- 既卒の面接は何回くらいありますか?
- 既卒になった理由を聞かれるのはなぜですか?
既卒の就活は不利なのでしょうか?
既卒の就活が一概に不利とはいえません。
確かに新卒一括採用を重視する企業もありますが、既卒者の採用に積極的な企業も増えているからです。
既卒者の強みは、卒業後の時間を通じて得た経験や気づきです。アルバイトやボランティア活動、自己啓発など、その期間をどう過ごしたかが重要です。
また、じっくりと自己分析や業界研究ができたことで、より明確な志望動機を持っていることも魅力となるでしょう。
ただし、ブランクをどう埋めるかという説明は必要です。自信を持って自分の成長をアピールし、なぜ今その企業で働きたいのかを具体的に伝えることが、成功の鍵となるでしょう。
既卒の面接は何回くらいありますか?
既卒の面接回数は企業によって異なりますが、2〜3回程度おこなう企業が一般的でしょう。
ただし、業界や職種、企業規模によっては、より多くの面接が行われる場合もあります。
典型的な流れとしては、1次面接(人事担当者)、2次面接(部門責任者)、最終面接(役員クラス)となるケースが多いでしょう。各面接の目的や評価ポイントが異なる可能性があるため、回数にかかわらず、毎回全力で臨むことが大切です。
既卒になった理由を聞かれるのはなぜですか?
既卒になった理由を聞かれるのは、主に以下の3点を確認するためです。
1つ目は、あなたの自己分析力と説明能力です。自分の経験を客観的に振り返り、明確に説明できるかを見ています。
2つ目は、その期間をどのように過ごし、何を学んだかです。成長や学びがあったかを確認します。
3つ目は、現在の就職に対する意欲です。なぜ今この企業に応募したのかを知りたいということです。ネガティブな理由であっても、そこからどのように学び、成長したかを説明することが重要です。前向きな姿勢で回答しましょう。
まとめ|既卒面接では念入りな準備と確かな自信がカギとなる
既卒での就職活動には、たしかに新卒とは異なる難しさがあります。
しかし、だからといって諦める必要はありません。卒業後の経験を通じて学んだことや気づきも、就職活動において武器となる可能性があります。
面接では、卒業後の活動について、それがいかに有意義なものであったかをアピールすることが重要です。自分の成長と将来的なキャリアプランを結び付けながら、志望先企業でどのように活躍していきたいかを述べましょう。
好印象を残すには、何より深い自己分析や企業研究が重要です。「その企業だからこそできること」を見つけ、自分の言葉で志望動機に落とし込みましょう。自分の持っている経験やスキルを使って、どのように企業の成長に貢献できるかを述べることも大切です。
十分な準備をし、自信を持って面接に臨んでください。自分ならではの視点と経験を活かし、企業に新しい価値をもたらす存在になることを目指しましょう。
| エージェント名 | 評価 | ポイント |
|---|---|---|
 >>キャリアスタート公式へ >>キャリアスタート公式へ |
高待遇の求人を多数保有し、高年収も目指せる! | |
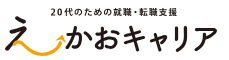 >> えーかおキャリア公式へ >> えーかおキャリア公式へ |
充実したサポートで定着しやすい企業に出会える! | |
 >>アメキャリ公式へ >>アメキャリ公式へ |
平均12時間のサポートで給与アップして就職可能! |