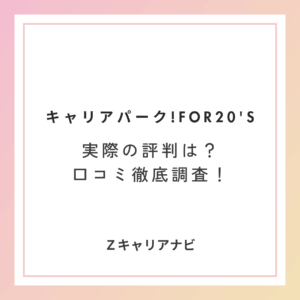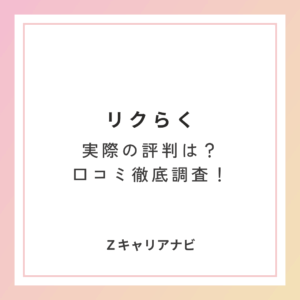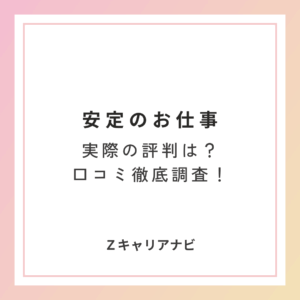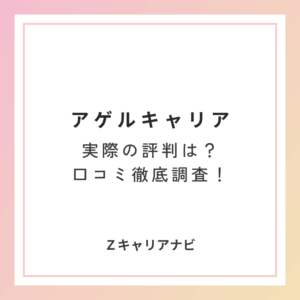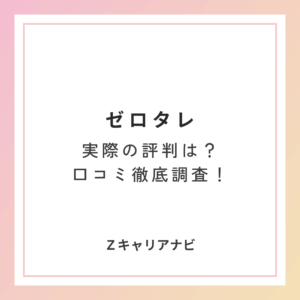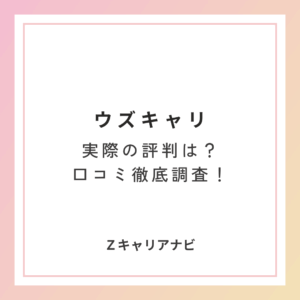「新卒で入社したけど仕事が合わないし辞めたい…」
「調べたら第二新卒に該当するみたいだけど就活して自分に合う職場を見つけられるかな…」
このように悩んでいる第二新卒の方も多いのではないでしょうか。
結論、第二新卒の就活は、正しい行動をとれば1〜3ヶ月程度で理想の職場に就職できます。
本記事では、第二新卒向けに就活で失敗しないための準備や成功するノウハウを紹介します。
現職の仕事から他の企業へ就職を考えている第二新卒の方は、最後までチェックしてみてください。
| エージェント名 | 評価 | ポイント |
|---|---|---|
 >>キャリアスタート公式へ >>キャリアスタート公式へ |
高待遇の求人を多数保有し、高年収も目指せる! | |
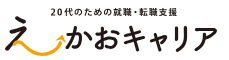 >> えーかおキャリア公式へ >> えーかおキャリア公式へ |
充実したサポートで定着しやすい企業に出会える! | |
 >>アメキャリ公式へ >>アメキャリ公式へ |
平均12時間のサポートで給与アップして就職可能! |
目次
第二新卒とは:学校を卒業後3年以内に離職した人
第二新卒とは、大学や専門学校を卒業してから3年以内に離職した人を指します。厚生労働省の調査によると、新卒で就職した人の約32〜37%が3年以内に退職しているようです。
つまり、約30%の新卒者が、思い描いていた職場環境とのギャップや、仕事が合わないと感じて、最初に入社した企業を退職していることになります。
しかし、第二新卒の時期であれば、まだ年齢が若く就職市場でも柔軟に対応できるため、新しい環境で再スタートしやすいです。
そのため、仕事を辞めて新たな就職先を探している第二新卒の方は、前向きに行動していきましょう。次章では、第二新卒の就活時に知っておきたい新卒と第二新卒の違いについて詳しく解説します。
参考:新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)を公表します|厚生労働省
第二新卒の就活時に知っておきたい新卒と第二新卒の違い
新卒と第二新卒の違いは、以下のとおり社会人経験があるかどうかです。
| 社会人経験 | 特徴 | |
|---|---|---|
| 新卒 | なし | 学校を卒業してはじめて就職する人 |
| 第二新卒 | あり(1〜3年) | 学校卒業後、就職して3年以内に就職を希望している人 |
上記のとおり新卒は、学校を卒業したばかりで社会に出るのがはじめての人たちを指し、企業はポテンシャルや将来の成長に期待して採用します。
一方、第二新卒は1〜3年の社会人経験を積んだ後、再び就職を検討している人たちを指し、企業は教育コスト削減と若い成長意欲に期待しています。
新卒と第二新卒では、企業から求められることが違う点も理解したうえで、就活を進めましょう。
第二新卒の就活需要が高い3つの理由
ここからは、第二新卒の就活需要が高い3つの理由について解説していきます。
新卒採用の予定数が下回る場合がある
企業が第二新卒を積極的に採用する理由の一つは、新卒採用で期待していた人数を確保できない場合があるからです。
「予定よりも採用人数が足りない…」という状況で、すぐに戦力として働ける第二新卒は企業にとって欠かせない存在です。
実際、少子高齢化の影響で新卒採用の競争は年々激化しています。そのため、第二新卒の需要が高まっていることがわかります。
事業が成長している企業は積極的に若手人材採用をしたい
事業が拡大している企業は、未来を担う若い人材を積極的に採用したいと考えています。
とくに第二新卒は、社会人経験を持ちつつも新しい環境に適応しやすいため、企業にとって非常に魅力的な存在と言えるでしょう。
また、第二新卒はすでに社会人としての基礎を身につけているため、企業側にとって教育の手間が新卒より少ない点も魅力です。
リクルートの調査では「事業拡大に伴い、若手の採用を重視する企業が増えている」とされており、とくにスタートアップ企業では、柔軟で吸収力の高い第二新卒の需要が高まっているようです。
もし、あなたが「もっと自分を成長させたい」「新しい環境で再挑戦したい」と考えているのであれば、事業拡大中の企業へ就職を目指してみてもよいでしょう。
企業側は新卒以上のポテンシャルを感じている
企業側は、第二新卒の人材に新卒以上のポテンシャルを感じているケースも多くあります。
新卒採用の場合、企業はゼロからの教育が必要ですが、第二新卒には基本的なビジネスマナーや業務の流れなど新卒で学んでいる強みがあります。
これらに加えて、若さや柔軟性もあるため、新しいことにも積極的に挑戦する姿勢も期待されやすいです。
このように第二新卒の立場は、社会人経験がありつつ、新しいことに柔軟に対応できる若さは企業にとって大きなアドバンテージとなります。
| エージェント名 | 評価 | ポイント |
|---|---|---|
 >>キャリアスタート公式へ >>キャリアスタート公式へ |
高待遇の求人を多数保有し、高年収も目指せる! | |
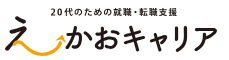 >> えーかおキャリア公式へ >> えーかおキャリア公式へ |
充実したサポートで定着しやすい企業に出会える! | |
 >>アメキャリ公式へ >>アメキャリ公式へ |
平均12時間のサポートで給与アップして就職可能! |
第二新卒の就活事情について
ここからは第二新卒の就活事情について、以下3つ紹介します。
第二新卒の採用は8割以上の企業が積極的
マイナビのデータによると、8割以上の企業が積極的に第二新卒を採用しており若手人材として重宝されています。
第二新卒が多くの企業に評価されている背景には、企業の人材不足が影響しています。
そのため、若手でありながら社会人経験がある第二新卒が注目されるようになったと言えるでしょう。
筆者が勤めていた企業の人事担当者も「第二新卒の若手を採用したい」と言っていた記憶があります。
このように、多くの企業があなたのような第二新卒を求めています。自分の魅力を引き出せる企業を粘り強く探してみてください。
参考:【2024年更新】第二新卒とは?何歳まで? 転職市場での重要性も紹介|マイナビジョブ20s
就活エージェントの利用も増えている
dodaの情報を参考にすると、第二新卒者による就活エージェントの利用が増えています。就活エージェントの利用が増えている理由は、以下のようなことが考えられます。
- 履歴書や職務経歴書の添削をしてほしい
- 面接のアドバイスを受けたい
- 企業側と交渉して欲しい
実際、就活を一人でしていると「本当に仕事が見つかるのか」「就職後にうまくやっていけるのか」など、心配ごとも増えるはずです。
もし、新たな就職を考えていて「どう進めていいか分からない」「一人で進めるのが不安」と感じているなら、第二新卒に強い就活エージェントを利用してみるとよいでしょう。
第二新卒者が就活に対して積極的になっている
近年、第二新卒の人たちが就活に対して積極的な動きになってきています。
dodaを運営しているパーソルキャリアの調べでは、2023年に第二新卒にあたる新社会人の登録数が、2011年と比べて約30倍に増えたことが報告されています。
3年も経てば、仕事や職場環境も本当に自分に合っているのかわかってくるため「自分に向いていない仕事だな…」と感じたら、別の企業へ就職を希望する人が多くなっているのも理由でしょう。
もし「今の仕事が自分に合っているのか分からない…」と悩んでいる方がいれば、就活エージェントに登録し、専門のアドバイザーに相談してみるのも一つの方法です。
参考:「新卒入社直後のdoda登録動向」最新版を発表|パーソルキャリア
第二新卒の就活が失敗する3つの原因
第二新卒の就活が失敗する3つの原因は、次のとおりです。
一つずつ詳しく解説します。
早期退職に対しての不安を企業が拭いきれていない
第二新卒が就活で苦戦する理由の一つは、企業側が「早期退職に対するリスク」を懸念していることです。
とくに、短期間で退職した経歴があると「すぐに辞めてしまうのではないのか…」と企業側からマイナス評価を受ける場合もあるでしょう。
そのため、第二新卒の就活では「前職では○○を学び、その経験を活かして今後は××の分野で長期的にキャリアを築きたい」と前職の経験を活かして、前向きに取り組んでいる旨を伝える必要があります。
早期退職の不安を取り除けるような、面接対策をしてみてください。
面接で自分の思いを伝えきれない
面接で自分の思いを伝えきれない場合も、就活が失敗する原因の一つです。面接では、自分の強みや就活への意欲を明確に話せないと、採用担当者にあなたの魅力が伝わりにくくなり、結果的に内定を逃してしまいます。
たしかに面接の際に無言で黙り込んでしまうと、採用担当者も「この人に仕事を任せるのは不安だな…」と感じてしまうかもしれません。
このため、面接では自分の考えや挑戦したいことなど、事前に伝えられるよう練習しておきましょう。
「なぜ就職したいのか」「新しい職場でどんな自分になりたいのか」紙に書き出して整理し、短くわかりやすく話せるようにしてみてるのもおすすめです。
就職先の内定が出る前に辞めてしまう
就職先の内定が出る前に辞めてしまうと、就活はうまくいかない場合があります。第二新卒の就活は、以下の手順で進めるため、内定から実際に働きはじめるまでには1〜3ヶ月が必要です。
- 求人探し:数日〜1週間
- 書類作成:数日
- 企業への応募:数日
- 企業からの連絡待ち:数日〜1週間
- 面接後の結果待ち:数日〜2週間
上記のとおり、すぐに働けるわけではないため、仕事ができない間は貯金を切り崩す生活になり、別のストレスを抱え込んでしまう可能性があります。
もし、金銭的なストレスを抱えてしまっては企業選びが雑になってしまい「就活に失敗してしまった…」となりかねません。
そのため、できる限り在職中に次の就職先を見つけておきましょう。
| エージェント名 | 評価 | ポイント |
|---|---|---|
 >>キャリアスタート公式へ >>キャリアスタート公式へ |
高待遇の求人を多数保有し、高年収も目指せる! | |
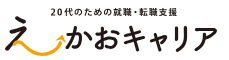 >> えーかおキャリア公式へ >> えーかおキャリア公式へ |
充実したサポートで定着しやすい企業に出会える! | |
 >>アメキャリ公式へ >>アメキャリ公式へ |
平均12時間のサポートで給与アップして就職可能! |
第二新卒の就活を成功させるための5ステップ
第二新卒の就活を成功させるためには、次の5ステップで進めてみてください。
詳しく解説します。
1.就職までの日程を決める
就活を成功させるためには、まずスケジュールをしっかりと立てることが大切です。計画を立てると、余裕を持って準備ができ、焦らず自分に合った職場を見つけやすくなります。
スケジュールがないまま進めてしまうと、どうしても準備が足りないまま就活しなければいけません。実際、就活にかかる期間は平均で1〜3ヶ月と言われています。
筆者が就活していたときは「3ヶ月以内に内定をもらう」というゴールを設定し、逆算して計画を立てていました。
事前に計画を立てておくと、以下のようにスムーズなスケジュール調整が可能です。
- 1週目は求人探し
- 2週目に応募書類の準備と応募開始
- 3〜4週目に面接の予定を組み
- 1〜2ヶ月は集中的に応募と面接を繰り返す
- 3ヶ月目に内定と現職の退職手続きを進める
上記のとおり事前に目標を立てておくことで、就活の流れはスムーズになります。現在、就活に悩んでいる方は、参考にしてみてください。
2.自分に合う仕事を探す
就活をはじめるとき、一番大事なのは「自分に合う仕事」を見つけることです。
「給料がよさそう」「仕事が楽しそう」など、安易な理由で飛びついてしまうと、職場の雰囲気が合わなかったり、仕事内容がイメージと違っていたりして、すぐに辞めてしまう場合があります。
就職に成功してもすぐに辞めてしまっては、今までの努力が水の泡です。そのため、就活の際は公式サイトや口コミ、SNSなどからしっかり情報収集しておきましょう。
3.応募書類を作成する
応募書類は、就活の成功を決める大事なポイントです。とくに第二新卒として新たなスタートを切るなら、これまでの経験や自分の強みをしっかり伝える必要があります。
履歴書や職務経歴書などの応募書類は、企業が最初にあなたを採用するかどうかを決める重要な書類です。実際、書類選考に通らなければ、就活のスタートラインにすら立てません。
そのため、応募書類を作成する際には「自分の経験や強みをどう伝えたらいいか」じっくり考えるようにして書類作成してみてください。
4.面接対策して応募する
面接対策をしっかりとおこなってから応募すると、内定の確率が高まりやすくなります。
企業の採用担当者が第二新卒に対して注目しているのは、あなたの「就職したい理由」「これからどうしていきたいのか」といった内容です。
就職したい理由やこれからの展望をうまく伝えられないと、採用担当者から「この人、前職と同じようにすぐ辞めるんじゃないか…」と不安を抱かせてしまいます。
そのため、準備不足で内定のチャンスを逃さないためにも、事前の面接対策はしっかりしてください。
面接対策の事前準備しておくことで、面接当日に落ち着いて自分の考えや気持ちを採用担当者にしっかり伝えられるでしょう。
5.在職中の企業で退職手続きを進める
就活を成功させるためには、在職中の企業に関する退職手続きを適切に進めておきましょう。退職手続きをスムーズにしておけば、次の企業でのスタートもスッキリした気持ちで取り組めます。
また、有給休暇が円滑に取得できたり、業務の引き継ぎもスムーズにおこなえたりと、退職したあとも良好な関係を築けます。
筆者のケースでは、今まで退職してきた企業の方々ともいまだに交流があり「就職した先でうまくいかなかったら、いつでも連絡してきて」と言われることも多々あります。
そのため、在職中の企業とも友好な関係が構築できるよう、退職手続きがスムーズにおこないながら就活を進めてみてください。
第二新卒の就活に困ったら就活エージェントの活用がおすすめ
第二新卒の就活がうまくいかずに悩んでいるなら、就活エージェントを利用するのがおすすめです。
就活エージェントは、プロとしてあなたの強みを見つけてくれたり、進め方のアドバイスをしてくれたりするため、迷いがちな企業選びもスムーズに決めやすくなります。
第二新卒の就活では「自分にはどのような仕事が向いているのか」「どうやってアピールすればいいのか」といった悩みがつきものです。
とくに、一度就職して退職を経験したあとは、次の就職で失敗したくないという気持ちが強くなる方も多いはずです。就活で失敗しないように、就活エージェントをうまく活用してみましょう。
次章では、第二新卒におすすめの就活エージェントを紹介します。
第二新卒の就活におすすめのエージェント|3選
第二新卒の就活におすすめのエージェント3つ厳選したので、それぞれ紹介します。
えーかおキャリア

【えーかおキャリアの特徴】
- 入社1年後の定着率が97%の実績がある
- 状況に合わせてサポートが受けられる
- キャリアアドバイザーがマンツーマンでサポートをしてくれる
「えーかおキャリア」は、第二新卒で再就職したいと考えている方に、おすすめの就活エージェントです。
とくに丁寧なサポートと入社1年後の定着率が97%と魅力的で、学歴や職歴に不安を抱える方でも安心して正社員を目指せます。
「就活がうまく行くのか心配…」「希望職種について相談してみたい…」このような気持ちがあるなら「えーかおキャリア」に無料登録して、プロからのアドバイスを受けてみましょう。
【こんな方におすすめ】
- 東京・大阪に住んでいる第二新卒の方
- 未経験の業界に挑戦したい方
- 就活を早めに済ませたい方
キャリアスタート

【キャリアスタートの特徴】
- 量より質をコンセプトに就活サポートをしている
- 面接対策のレベルが高い
- 高年収の中小企業求人が多い
「キャリアスタート」の大きな魅力は、量より質を重視した就活サポートを提供している点です。とくに面接対策には力を入れており、実践的なアドバイスを受けられるため、面接に自信がない方でもしっかりと準備ができます。
また、高年収の中小企業の求人が多いのも特徴で、待遇面を重視する方にもおすすめです。
「学歴に自信がないけれど正社員を目指したい…」「できるだけ早く内定をもらいたい…」と思っているなら、「キャリアスタート」を活用してみてください。
【こんな方におすすめ】
- 東京・名古屋・大阪・京都に住んでいる第二新卒の方
- ブラック企業へ入社したくない方
- 書類選考になかなか通過しない方
アメキャリ

【アメキャリの特徴】
- Google顧客満足度が★4.9と高評価
- スマホ面談をしている
- 土日もマンツーマンサポート実施している
「アメキャリ」の一番の特徴は、Google顧客満足度4.9で高評価を得られている点です。このように実際、利用した方の信頼を得ているからこそ、安心して相談できます。
また、土日も対応してくれているため、平日忙しい方でも自分のペースで進められます。「忙しくて就職活動の時間がない…」と悩んでいる方は、一度無料登録して相談してみてください。
【こんな方におすすめ】
- 20代・既卒・フリーターで就職活動がはじめての方
- やりたいことが決まってない方
- 社会人経験が一度もない方
第二新卒の就活に関するよくある質問
第二新卒の就活に関するよくある質問について、3つ紹介していきます。
第二新卒は最低何ヶ月の在籍が必要ですか?
第二新卒の就職には、退職後であれば約1ヶ月、在職中なら約3ヶ月かかるのが一般的です。
また、就活をはじめるタイミングとしては、1〜3月や7〜9月がおすすめの時期です。
第二新卒はなぜ有利なのでしょうか?
第二新卒が就活で有利といわれるのは、次のような理由があります。
- 社会人経験をアピールできる
- 若さや柔軟性が評価される
- 新卒より教育コストを削減できる
など
このような理由から、第二新卒の就活は新卒とは違った点が有利とされています。
第二新卒は何年勤めた人ですか?
第二新卒とは、新卒入社後2~3年勤務した後に就活をしている人、もしくは新卒入社をせずに卒業後2~3年経過してから就活をする人を指すのが一般的です。
まとめ:第二新卒の就活は企業選びが大切
第二新卒で就活を失敗しないようにするのは、何よりも「自分に合う企業選び」ができるかどうかです。
とはいえ、新卒の就活以来になるので「本当に合う企業が見つかるのか…」「応募書類や面接でうまくアピールできるか心配…」など、不安を抱える方も少なくないでしょう。
そうした不安を抱える学生の方におすすめできるのが、就活エージェントです。就活エージェントでは、就活生の希望や適性を理解したうえで、マッチする企業を紹介してくれます。
また、応募書類の添削や面接対策のサポートも充実しているので、安心して就活を進められます。
就活エージェントのサポートをうまく利用しながら、新しい一歩を踏み出しましょう。
| エージェント名 | 評価 | ポイント |
|---|---|---|
 >>キャリアスタート公式へ >>キャリアスタート公式へ |
高待遇の求人を多数保有し、高年収も目指せる! | |
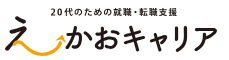 >> えーかおキャリア公式へ >> えーかおキャリア公式へ |
充実したサポートで定着しやすい企業に出会える! | |
 >>アメキャリ公式へ >>アメキャリ公式へ |
平均12時間のサポートで給与アップして就職可能! |